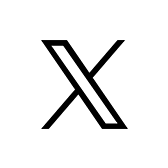iDeCo・変額保険・積立NISAの違いは?仕組みを理解して賢く資産運用しよう
将来の老後資金のために

さまざまな資産運用のうち、将来の老後資金形成のためにはどのような方法があるかについて紹介します。
銀行口座へ預金
老後資金対策で「お金を貯める」方法として多くの人が実践しているのは、「銀行預金」です。銀行預金は、資金を口座に貯めておくことで資金確保をする仕組みです。
しかし、現在の銀行普通預金の金利は0.001%程度で設定している金融機関が多く、金利で増える見込みはほぼありません)。一方で、いつでも好きな時に入出金ができるため、流動性が高いというメリットがあります。
株式投資
資産運用と聞くと、株式投資をイメージする人も多いでしょう。
確かに株式投資は、昔も今も普遍的に人気の資産運用です。しかし、老後資金形成を目的とした資産運用として、株式投資は必ずしもベストではない場合もあります。株式投資の利益の出し方は、「安く買って高く売る」という点です。
一方で株価の変動については、経済や投資に精通していても、先読みをできるものではありません。場合によっては大きく損失が出ることもあります。老後資金形成では、損失のリスクは少しでも排除した方が安心です。
投資信託
投資信託は、老後資金対策として安心できるポイントを抑えた商品です。
無料または少額の手数料のみで、あとはプロが極力損失を出さないように運用してくれるのが「投資信託」です。プロが運用するため、経済の知識やこれまでの投資経験は大きく関係しません。特に投資初心者で、老後資金対策として今からできる資産運用を検討している人にはおすすめの商品です。
おすすめの資産運用3種類
投資信託を使って、比較的安定して老後資金のための資産運用が可能なのは、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」「変額保険」「積立NISA」の3種類です。
いずれの方法でも、投資信託の利点を生かして長期的に運用していく仕組みです。各商品の概要について、詳しくは次の項目で紹介します。
おすすめ資産運用商品の仕組み

iDeCo、変額保険、積立NISAについて、それぞれの仕組みを紹介します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoとは、正式名称を「個人型確定拠出年金」と言います。iDeCoは、国民年金や厚生年金など、老後にもらえる年金に加えて自主的に上乗せ年金を持つイメージです。加入できる期間は20歳から65歳まで、原則として中途解約はできません。
iDeCo対象になっている金融商品のなかから、自分でいくつか選んで購入します。その中で投資信託商品を選ぶことができます。また、会社員等の場合は、加入上限金額が定められている場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。
生命保険(変額保険)
生命保険の一種である変額保険も、老後の資産形成として選ばれることが多いです。変額保険は、保険料の一部を投資信託や株で運用する保険商品です。元本割れのリスクはゼロではありませんが、保険会社が最低保証金額や死亡保険金に関して、確約している場合がほとんどです。
積立NISA
積立NISAは最長20年の非課税期間があり、年間40万円までの投資金額でコツコツ積立をしていく仕組みです。一般NISAは、年間非課税投資額を使って一括で大きな商品を購入できますが、積立NISAでは「積立」が前提です。毎月コツコツ積み立てるため、より安全に分散投資ができます。
また、積立NISAで選べる商品は、手数料がゼロまたは格安であることを条件に選別されています。そのため、積立NISAで投資信託を選んでも、手数料を気にせずに長期運用が可能です。
各商品のメリット・デメリット

上記3つの商品のメリット、デメリットを紹介します。
メリット
いずれの商品も長期運用を前提としており、リスク分散が可能です。
iDeCoは、加入後65歳まで原則として解約できません。変額保険は、加入時に設定した期間は毎月保険料を支払います。積立NISAは、最長20年の非課税期間が設けられています。
長期投資のメリットは少額ずつ資金を分散して投資できるため、景気の影響を受けにくく、運用結果が安定しやすいという点です。
利用できる税制優遇は活用しよう
他にも、利用できる税制優遇があることはメリットといえます。iDeCoは、掛け金が全額社会保険料控除になります。変額保険は、保険料が生命保険料控除の対象です。積立NISAは、最長20年および毎年40万円までの投資金額に対して非課税となります。
デメリット
この3商品に共通するデメリットは、短期間で解約すると損をするリスクがあるということです。
いずれも長期運用を目的としているため、短期で解約してしまうと元本割れのリスクが非常に高い仕組みになっています。またそもそもiDeCoでは、65歳までの中途解約や、貯まっている資金の一時取り出しなどが原則として一切できません。
自身のライフスタイルに合わせて活用しよう

メリットやデメリットを把握したうえで、自身にとってどのように活用していけばよいか、参考になるポイントを解説していきます。
まずライフプランの確認が必要
現在単身世帯か家族世帯かによっても、将来のライフプランは変わってきます。端的に言うと、住宅ローンの有無やその期間、子どもの成長過程における教育資金の準備の可否などです。
まず自身や家族のライフプランを把握し、将来のビジョンを明確にしたうえで、どの資産運用を活用するのが効果的か判断すると良いでしょう。
会社員など給与所得者の場合
会社員など給与所得者の場合、厚生年金に加入しているので、将来は老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらも受け取ることができます。
さらに現役世代のうちに資産運用をするとしたら、積立NISAがおすすめです。上記で紹介した3商品のうち、最も一回当たりの投資金額が少なくて済みます。金融機関によって差がありますが、月1,000円程度から始めることが可能です。
教育資金や住宅ローンの出費と重なる時期でも、月数千円程度の積立であれば、大きな負担になることなく継続しやすいです。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、国民年金のみ加入し、将来は老齢基礎年金のみ受給です。老齢基礎年金の満額は、2021年(令和3年)支給分で年額約78万円です。月にすると約6.5万円ということになります。これ以外の老後資金は、自分で準備しておくということです。
そこで、個人事業主にはiDeCoがおすすめです。iDeCoは老後資金形成に特化しており、一度加入すると途中解約ができません。つまり、しっかり老後資金が確保できます。加入時に選んだ投資商品の成果によっては、運用額以上に受け取り可能です。掛け金が全額社会保険料控除になるのも、個人事業主には嬉しい節税ポイントです。
変額保険の活用
変額保険は、どのライフスタイルの人が、どのタイミングで始めても良い商品です。生命保険の一種ではあるものの、資産形成効果が高いことから、資産運用のひとつとして活用できます。前述したiDeCoや積立NISAと並行して、自身のポートフォリオにひとつ組み込んでおくことをおすすめします。
また、変額保険では死亡保険金の最低額は保証されているため、運用結果の如何を問わず、遺族保障としてまとまった資金を遺すことができ安心です。
まとめ
長期運用で安心して継続するために、おすすめの3商品(iDeCo、変額保険、積立NISA)を解説しました。自身や家族のライフプランを練った上で、最適な資産運用を選ぶ参考にしてみてください。
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。